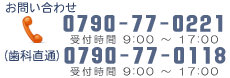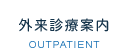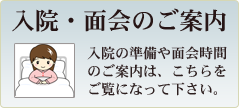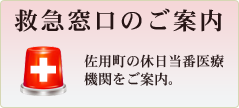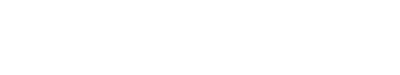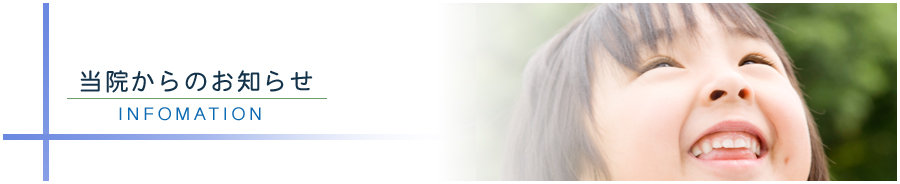
 身体拘束最小化のための指針
身体拘束最小化のための指針2025/6/1
身体的拘束最小化のための指針
1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者様の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では、患者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2.身体的拘束適正化のための体制
身体的拘束最小化チームの設置
身体的拘束最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置し、会議開催が必要な場合は、医療安全管理対策委員会で協議します。
1)チーム活動の内容
①身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底する。
②身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
③身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う。
④身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する。
⑤当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う。
2)身体的拘束最小化チームの構成員
内科医師・薬剤師・看護師長・看護師・介護福祉士
3.身体的拘束最小化に向けての基本指針
身体的拘束の定義
抑制帯等、患者様の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体的拘束その他、入院患者様の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロ手引き(2001年3月)」の中であげている行為を下に示します。
1)徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらないように手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつける。
6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルを付ける。
7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8)脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10)行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11)自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。
4.やむを得ず身体的拘束を行う場合
患者様または他の患者様の生命または身体を保護するための措置として、「対象の状態」の1~5のいずれかの状態であり、かつ、「対象の置かれた状況」の1~3の全てを満たす状態にある場合は、医療者複数で協議し、患者様・ご家族様への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、例外的に必要最小限の身体的拘束を行うことがあります。
「対象の状態」
1.激しい体動により転倒・転落の危険が高い(転倒の危険)
2.認知障害、興奮、不穏等があり身辺の危険を予知できない(認識障害)
3・暴力行為により、自傷、他人に損傷を与える危険がある(破壊・粗暴行為)
4.医療機器やライン、チューブ類を抜去しようとし治療が安全に行えない(治療が円滑に進まない)
5.病的反射や不随意運動により、自分の意思で体動を抑えられない(その他)
「対象の置かれた状況」
1.
1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者様の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では、患者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2.身体的拘束適正化のための体制
身体的拘束最小化チームの設置
身体的拘束最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置し、会議開催が必要な場合は、医療安全管理対策委員会で協議します。
1)チーム活動の内容
①身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底する。
②身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
③身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う。
④身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する。
⑤当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う。
2)身体的拘束最小化チームの構成員
内科医師・薬剤師・看護師長・看護師・介護福祉士
3.身体的拘束最小化に向けての基本指針
身体的拘束の定義
抑制帯等、患者様の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体的拘束その他、入院患者様の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロ手引き(2001年3月)」の中であげている行為を下に示します。
1)徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらないように手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつける。
6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルを付ける。
7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8)脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10)行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11)自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。
4.やむを得ず身体的拘束を行う場合
患者様または他の患者様の生命または身体を保護するための措置として、「対象の状態」の1~5のいずれかの状態であり、かつ、「対象の置かれた状況」の1~3の全てを満たす状態にある場合は、医療者複数で協議し、患者様・ご家族様への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、例外的に必要最小限の身体的拘束を行うことがあります。
「対象の状態」
1.激しい体動により転倒・転落の危険が高い(転倒の危険)
2.認知障害、興奮、不穏等があり身辺の危険を予知できない(認識障害)
3・暴力行為により、自傷、他人に損傷を与える危険がある(破壊・粗暴行為)
4.医療機器やライン、チューブ類を抜去しようとし治療が安全に行えない(治療が円滑に進まない)
5.病的反射や不随意運動により、自分の意思で体動を抑えられない(その他)
「対象の置かれた状況」
1.